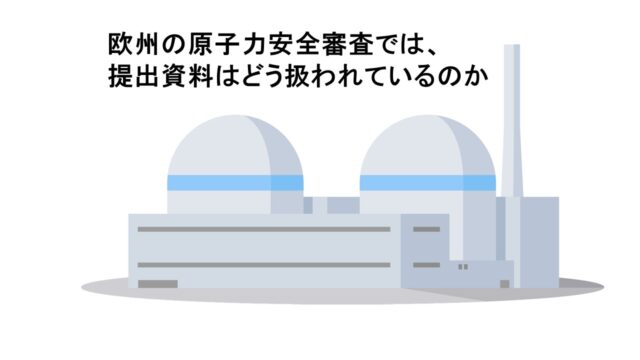なぜ、業務の「視える化」は難しく感じられるのか ――それは「未知への挑戦」だからではないか 第2回

業務の視える化が重要だということは、多くの人が分かっている。
仕事を改革し、よりまっとうな形にしていくには、業務の全体像を把握する必要がある。
効率化を進めるにも、判断の根拠を残すにも、視える化は避けて通れない。
それでも、多くの組織で業務の視える化は進んでいない。
この事実こそが、私たちが向き合うべき出発点ではないだろうか。
理由は、「重要性が理解されていないから」でも、「現場の意識が低いから」でもない。
もっと現実的で、もっと構造的な理由がある。
業務の視える化は、しばしば「改善」の一環として語られる。
しかし実際には、視える化とは、すでに分かっている業務を整理する作業ではない。
これまで把握が不十分だった業務、分かったつもりで運用してきた仕事の実態に、初めて正面から向き合う行為である。
どこまで分かっていなかったのかは、やってみるまで分からない。
どこに無駄や抜けがあるのか、どの業務が誰の判断に依存しているのか。
そうしたことは、着手して初めて輪郭を持つ。
つまり業務の視える化は、既知の改善ではなく、「未知への挑戦」なのだ。
未知である以上、工数も影響範囲も読めない。
通常業務にどれほどの負荷がかかるのかも分からない。
忙しい現場ほど、「今それに取り組む余裕はない」と感じるのは、きわめて自然な反応である。
さらに言えば、管理者自身も、業務全体が完全には見えていないことを、どこかで感じ取っている場合がある。
業務は細分化され、分業が進み、非正規職員や派遣、委託に実務が委ねられている。
仕事は回っているが、何がどこまで行われているのか、判断の前提は何か。
誰も全体像を掴めないまま、日々の業務が積み重なっていく。
この状態で視える化に踏み出すことは、これまでの把握の仕方が限界に来ていることを認める行為にもなる。
それは能力の問題ではない。
仕事の設計そのものが、時代の前提に合わなくなっているという事実に向き合うことだ。
心理的な負担が大きいのも、無理はない。
こうした背景があるため、業務の視える化は「難しすぎる」「自分たちではできない」「高いコンサルを入れないと無理だ」と感じられがちだ。
また、「そんな暇はない」という感覚も、決して言い訳ではない。
未知への挑戦を、日常業務の延長で引き受けることは、本来とても重い。
だからこそ、業務の視える化は避けられてきた。
それは怠慢でも抵抗でもなく、日本の仕事が長く、人の記憶や善意、継続的な在籍を前提に成立してきた結果でもある。
しかし、その前提はすでに崩れている。
人は入れ替わり、非正規比率は高まり、説明責任は重くなった。
業務の視える化は、やるかやらないかの問題ではない。
いつ向き合うかの問題になっている。
文書管理や公文書管理について、
ほかの記事も書いています。
よろしければ、
ブログ一覧からご覧ください。