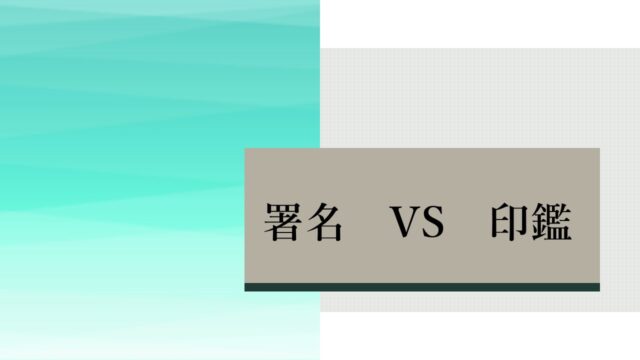公文書管理を「文書整理」で終わらせないために ― 業務プロセスから考える、説明責任のための公文書管理 ―

公文書管理という言葉を聞くと、 多くの場合、文書の整理方法や保存期間、電子化の話題が思い浮かびます。
しかし、自治体で繰り返される 「意思決定の経緯が分からない」 「後から検証できない」 「記録が残っていなかった」 という問題は、 単に文書管理の技術が不足しているから起きているのでしょうか。
私はそうは思いません。 問題の本質は、公文書管理が『文書整理』の延長として捉えられ、 業務そのものが説明責任を前提に設計されていないことにあります。
文書は結果であり、出発点ではない
多くの自治体では、 業務が行われた結果として文書が作成され、 その後に保存・整理のルールが適用されます。
この流れ自体は間違いではありませんが、 それだけでは、 「なぜその判断が行われたのか」 「他に選択肢はなかったのか」 といった、 説明責任の核心部分が抜け落ちやすくなります。
本来、考えるべき順序は逆です。
- その業務は、どのような目的で行われているのか
- どの段階で、誰が判断を行っているのか
- その判断は、後から説明や検証が求められるものか
こうした業務プロセスの整理・分析を行った上で、 初めて 「では、どのような記録を残すべきか」 が見えてきます。
記録は出発点ではなく、 業務が正しく行われたことを示す『結果』であり、『証拠』なのです。
ISO30301が示している、もう一つの公文書管理
この考え方を国際標準として体系化したものが、 ISO30301(日本では JIS X 30301)です。
ISO30301は、 文書をどう整理するか、 どのシステムを使うか、 といった話から始まりません。
まず求めているのは、
- 組織の業務は、どのようなプロセスで構成されているか
- その中で、説明責任を伴う判断や行為はどこか
- 記録が作成されなかった場合、どのようなリスクが生じるか
といった点を、 業務の流れに即して把握することです。
その結果として、 業務が適切に行われたことを後から検証できる記録を、 組織の責任として確実に残す仕組みを整える。
ISO30301は、 公文書管理を 行政運営そのものの説明責任を支えるマネジメントの問題として 捉え直す規格だと言えます。
なぜ文書整理だけでは不十分なのか
不祥事やトラブルが起きた後、 第三者委員会や調査委員会が設置される場面を、 私たちは何度も目にしてきました。
その際、よく聞かれるのが 「記録が残っていなかったため、検証できない」 という言葉です。
しかし、これは 「担当者が文書を残さなかった」 という個人の問題ではありません。
- どの業務で
- どの判断について
- 記録を残す必要があるのか
が、 組織として定義されていなかったことの結果です。
文書整理をどれだけ厳格にしても、 そもそも 「残すべき記録」が設計されていなければ、 説明責任を果たすことはできません。
本当に不足しているのは「業務プロセス分析の力」
官民を問わず、日本で軽視されてきたのは、 文書管理そのものではなく、 業務プロセスを構造的に捉える力ではないでしょうか。
業務プロセス分析とは、 単にフロー図を描くことではありません。
- 業務の目的は何か
- 判断が集中するポイントはどこか
- 例外や逸脱はどこで起きやすいか
- どこが説明責任の核心になるか
を考え抜く作業です。
この能力は、 短期間の研修や制度導入だけで身につくものではありません。 現場での経験と、 振り返りを重ねる地道な努力によって、 少しずつ培われていくものです。
制度導入よりも、能力の蓄積を
ISO30301は、 魔法のように問題を解決する制度ではありません。
むしろ、 業務プロセス分析という、 日本で長く後回しにされてきた能力と正面から向き合うことを 組織に求める規格です。
ここから先は、立場ごとに、あらためて問いを分けて考える必要があります。
【結び①:首長・副市長・幹部向け】
公文書管理は、 担当部署に任せれば足りる業務ではありません。
どの業務で、 どのような判断が行われ、 それが後から説明できる形になっているのか。
これは、 行政運営そのものの設計に関わる問題です。
制度やシステムを整えること以上に、 業務プロセスを見渡し、 「説明できる行政」になっているかを問い続けること。
それは、 首長・幹部にしか担えない責任でもあります。
【結び②:実務担当者・現場職員向け】
公文書管理は、 単なる文書整理の作業ではありません。
日々行っている業務の中で、 どこが重要な判断点なのか、 どの部分が後から説明を求められるのかを意識すること。
その積み重ねが、 業務プロセス分析の力を育て、 結果として、 記録が自然に残る業務につながっていきます。